“自分の色”を発揮し、人生をスタイリングしよう!
―学んだ知識をどう使うか。それが本当のスタート―

- yukiko(ゆきこ)
- 色彩総合プロデュース「スタイル プロモーション」代表 色彩総合プロデューサー&ファッションスタイリスト 色彩講師 本格焼酎イベントプロデューサー ライター アルパ奏者 焼酎スタイリスト 日本酒スタイリスト
新卒で株式会社永谷園入社。生産部門に従事しながらスタイリスト養成学校へ通う。色彩検定1級取得。「色が強み」のファッションスタイリストに転身し、ファッション誌、CMなどに携わる。ブランドイメージを創り上げる色彩戦略、ビジュアルプロモーションを担う。2005年、教育機関や企業で講師としてプロ育成に注力し、受講生は8000人を超える。2010年から色彩総合プロデュース「スタイル プロモーション」(事務所最寄り:青山一丁目)主宰。撮影や取材、講演、検定対策、企業研修、商品企画、イベント企画運営など行う。2013年より日本の伝統や食文化を紹介する「色と食の旅プロジェクト」、2014年より地域の特色をPRする「鹿児島芋焼酎コミュニティクラブ」を東京発信。生産者と生活者をつなぐ色彩活動が多数のメディアで紹介。アルパ奏者(ラテンハープ)として東京ビッグサイトなどイベント演奏多数。当「Career Groove」の取材記事の執筆も多数担当している。
「色」の効果を最大限に活かし、人と人を結びつける

―yukikoさんの活動内容について説明をお願いします。
色彩総合プロデュース「STYLE promotion」(以下、「スタイル プロモーション」)の主宰をしています。「色」の有効活用を提唱し、色彩戦略、ブランディング、色彩教育などを行っています。色彩効果を高めたい業界すべてがビジネスパートナーです。
簡単に言うと「色屋さん」ですね(笑)。商品企画、ファッション誌・TVやWEBの撮影・取材、イベント運営、学校教育や色彩検定などの検定対策、パーソナルカラーのトレーナー育成、企業の研修、講演も行います。音楽活動としてアルパ(中南米のハープ)の演奏もしています。
―イベントの運営というと、どのようなことをしていますか?
色をテーマに地域で継承される伝統や食文化を伝える「色と食の旅プロジェクト」や、國酒(日本のお酒)である本格焼酎と地域の特色を発信する「かごしま芋焼酎コミュニティナイト」を東京で開催しています。
「色と食の旅プロジェクト」は、必ずサブタイトルに色の名前をつけています。『隠れ旬を味わう!オイスター活力祭』では東日本大震災をきっかけに漁業の道に進んだ宮城県石巻市荻浜地区の30代漁師を東京にお呼びし、水産業の今を伝えるトークセッションや地元漁師が好む“隠れ旬”と呼ばれる牡蠣を食べてもらったり。
「かごしま芋焼酎コミュニティナイト」では、鹿児島県酒造組合および鹿児島県酒造青年会と連携し、スタイリストとして蔵元の皆さんと一緒に“おしゃれで親しみやすい本格焼酎の楽しみ方”を東京発信しています。鹿児島県庁、観光連盟、特産品協会など、地域組織や企業と協力して展開しています。
参加者は、東京にいながら地域色豊かな各地の旬の食材、文化を楽しめます。イベントがきっかけで実際に現地へ旅行したり、焼酎を取り寄せて自宅で楽しんだり。このように東京と地域を結ぶような役割を担っています。
最近は本格焼酎の仕事が増えてきて、周囲から「たいそうなお酒好き女子」と思われています(笑)。本当は3杯くらいしか飲めないんですけどね。
―なるほど(笑)。そもそも、yukikoさんが「色」に関する仕事をしようと思ったきっかけは?
学生時代は夢もなく、やりたいことが何もなかったんです。大学の就職課で雑誌を開いたら「カラーコーディネーター」という単語が目に飛び込んできて。その瞬間、「私、これを一生の仕事にするかも」ってビビッときたんです。直感ですね。
―昔から、色へのご興味があったのですか。
記憶をたどると、鹿児島県の伝統工芸品である「島津薩摩切子」がきっかけだと思っています。母方が鹿児島の出身で、幼少期に祖母と仙巌園([せんげんえん]/鹿児島の名勝地)や併設の「尚古集成館」([しょうこしゅうせいかん]/2015年7月世界文化遺産登録)の「島津薩摩切子」を見たんです。
「なんて綺麗なんだろう、宝石みたい!」と子どもながらに感動していて。その記憶が、ずっと眠ってはいたんですね。
 島津藩直系の(株)島津興業 薩摩ガラス工芸「島津薩摩切子」。職人の手作業でつくられる鹿児島県の伝統工芸品で、「色と食の旅プロジェクト」~島津紫の煌めき~ のメインアイテムだ。
【オールドファッションドタンブラー[島津紫]】(協力:銀座 焼酎BAR SAKURAJIMA)
島津藩直系の(株)島津興業 薩摩ガラス工芸「島津薩摩切子」。職人の手作業でつくられる鹿児島県の伝統工芸品で、「色と食の旅プロジェクト」~島津紫の煌めき~ のメインアイテムだ。
【オールドファッションドタンブラー[島津紫]】(協力:銀座 焼酎BAR SAKURAJIMA)
―実際に色彩を学び、資格を取ると、どのような仕事に活かせるのでしょうか?
色を使わない業界はないので、仕事に活かすのは自分の知識とアイデアと、行動力次第ですね。重要なのは資格をどう仕事に結びつけるか。現実的に活かせなければ意味がないので、私の生徒には実践力を身につける方法も教えています。
―yukikoさんが考える色彩の社会的役割というと何でしょう?
色は、生産者や作り手の気持ちをエンドユーザーや社会に伝える、一種のコミュニケーションツールだと思っています。
たとえば、商品パッケージをつくる時、「目立つ色=赤」と考える人が多いのですが、状況によっては必ずしも「赤」が目立つわけではありません。また、エンドユーザーが受けるイメージとそぐわなければ効果が得られません。
作り手と受け手、両者のバランスがとても大事なんですね。そのために私が潤滑油として間に入りコントロールをしているという感じです。
―今のお仕事のやりがいを感じる時は、どんな時ですか?
私にとって色は「人生のパートナー」です。ですから“色に嘘をつかない”と心に決めています。商品や作り手に対してきちんと向き合って色を決めないと、いずれ違和感が形になって現れてくるんです。
商品自体が売り上げや信用につながるのはもちろん、色彩によってさらに“嬉しい、温かい”といった心理的効果を与えるので、私自身の心も選んだ色を通して客観的に読めてしまうんです。だから常に本気です。“本当の気持ち”で向き合わないと妥協したことがのちの自分にバレます(笑)。
作り手とエンドユーザーの間で相乗効果を生みだせた時、色に嘘をつかないでいられた自分を実感できます。そんな時に、やりがいを感じますね。
突然襲った悲運―夢が閉ざされ、すべてが“ゼロ”に

―yukikoさんは色に対してとても誠実で、プロデューサーというより職人に近いですよね。そこまで色に対する想いを深められたのは、何か理由があったのでしょうか。
そうですね。クライアントから「色彩表現の職人」と言われます(笑)。まず、そこに至るまでの経緯をお話ししますね。
就職活動では色に関わる仕事がしたくて、アパレルや広告代理店など、いろいろな業界を見ました。そのなかでも商品パッケージやCMにオリジナリティのある永谷園に入社しました。
配属されたのは生産部門の事務職。希望していた商品企画ではありませんでしたが、製造部分に携わったことは、現在蔵元や生産者と一緒に活動をするうえで糧になっています。
ものづくりの初期段階にいて、完成品がCMでどのようにイメージ戦略されているかを社内にいて感じることができました。そこから、イメージやブランドを創り上げる「スタイリスト」に興味が湧いて、会社に許可を取って週3回、仕事終わりにスタイリストの学校に通っていました。
そのうちに展示会のお手伝いなどが増えて手一杯になり、退職を決めてそのまま独立。OLの経験から「普通のスタイリストよりも事務能力があって仕事が早い」とクライアントから重宝がられて、たくさん仕事をいただきました。人や環境にとても恵まれていましたね。
シャネルなど一流ブランドを扱うハイファッション誌にも関わるようになっていきました。雑誌において、イメージを創り上げる最高峰は『VOGUE(ヴォーグ)』や『ELLE(エル)』のようなハイファッション誌だと思って、モードの世界にのめり込んでいきました。
けれども、そんなある日、左ひざが突然腫れて曲がらなくなったんです。足を引きずって歩く状態。検査の結果、病的な心配はなかったものの、完治まで3か月から1年くらいかかると言われて……。
―えっ 突然に、ですか?
そう。今はもう全く問題ないんですけれどね。 でも、そのタイミングで、目標だったハイファッションの世界から専属の声がかかったんです。すぐに来てほしいという要望のなか、立ったり座ったりするのも不自由な状態。……結局その話は、無かったことになってしまったんです。
当時、ハイファッション誌に携わるには空きがなければ入れない狭き門。ようやくつかんだ夢が目の前にあったのに、それが自分の本意でない理由で断たれてしまった。「一度断ったら次はないと思って、チャンスを大事にしなさい」と育ってきただけに、すっごくショックで。「なんでこのタイミングで!?」と本当に悔しい気持ちでいっぱいになりました。
その後、生活のためにも、あえてファッションとは無関係のメーカーに再就職し、それまでに関わった仕事の資料をすべて捨てました。本気でスタイリストを辞める覚悟だったんです。そこまでしないと、新たな道へ踏み出すことができなかった。
しばらくは、ファッション誌も見る気が起きない、特に本屋に行きたくない状態が続きましたね。
―そんなつらい時期があったのですね……。
本屋に行くと、平置きに並べられたファッション誌を見ることになります。私が載るはずだった世界と接触するのがつらくて。
でも、スタイリストを辞めて1年半くらい経ったころ、しだいに本屋に足を運べるようになりました。色使いがきれいな写真集を見て心が和んだり、ワクワクする自分がいたんです。
やっぱり色に関わっていたいと思っている。それほど自分に必要ならそれを信じて進もうと心に決め、3年間のOL生活を卒業し、もう一度独立しました。
自分の意思と関係のない出来事によって、何もかもがなくなる“ゼロ”の状態になった時、初めて「自分にとって本当に大切なもの」、「手放してはいけないもの」がわかったんです。応援してくれる人たちのありがたみも。色と自分に対して真剣に向き合えたきっかけになります。
―それから開拓していくのは相当、大変だったのでは。
手探りでしたね。皆と同じことをしても意味がないとクリエイターの経験上わかっていたので、“自分にしかできないこと”を模索しました。
色の知識と実践経験があったので「カラーコーディネーターです」と掲げていたら、細々と仕事が入るようになり、ファッションスタイリストの仕事もできるようになって。本当に、色に助けられましたね。
―“ゼロ”になった経験から、今思うことはありますか?
「あの出来事がなければ、私は今、ハイファッションの世界にいたのかもしれない」。でもそれを“後悔”と解釈したら、一生悔やむ出来事になってしまう。だから「この道に進んで正しかった」と思えるように仕事をしようと考えました。“ゼロ”の経験をプラスに変えよう、と。
その意識で前進してきたので、今も後悔という言葉はないんです。この道だからこそ、ファッション業界だけではなく酒造業や農業、水産業など地域で出会う方々との接点があり、生の声が聞けます。それがとても楽しい。
ビジネスの先輩から「カラーコーディネーターやスタイリストはたくさんいるけど、“色彩”を総合的にアプローチして自らが表現者になっている人はいない」と言われます。それって私の「オリジナルの色」であり「色彩表現」。
10年経った今、ようやくあの出来事はあるべくしてあったのだと、私をここまで導いてくれた永谷園や再就職したメーカー、蔵元や生産者、皆さんに感謝なんです。
ある出会いをきっかけに、日本の伝統文化を伝える立場に
 無形文化財指定の鎚起銅器[ついきどうき]。重ね合わせた銅板を金鎚で打ち起こして形成する。
左から:スイングカップ[海UMI]/スイングカップ[月TSUKI]/急須 口打出 打出肌紫金色(協力:玉川堂・新潟県)
無形文化財指定の鎚起銅器[ついきどうき]。重ね合わせた銅板を金鎚で打ち起こして形成する。
左から:スイングカップ[海UMI]/スイングカップ[月TSUKI]/急須 口打出 打出肌紫金色(協力:玉川堂・新潟県)
―色と地域の文化のイベント運営をするようになったきっかけというのは?
スペイン人のジュエリーデザイナーを取材した時、「尊敬するアーティストはノリオ・タマガワ」と熱く語ってくれました。玉川宣夫[たまがわ のりお]氏とは、新潟県の株式会社玉川堂[ぎょくせんどう]に在籍している、木目金(※)を手がける金工の人間国宝の方です。
(※[もくめがね]/異なる金属を重ね合わせて打ち起こし、木目調を生み出す伝統工芸)当時私は存じ上げていなくて……。色彩美あふれる自国の伝統文化を、海外の方から教わった事実に衝撃を受けました。
「日本人として日本のことをちゃんと知っておきたい」 「同世代や若い世代はどの程度まで“メードインジャパン”の素晴らしさを理解しているのだろう」 「伝統色があるように、“伝統”は受け継ぐ人がいなければ途絶えてしまう。私なりのやり方でわかりやすく伝えていきたい」 ……それが、イベントを始めたのがきっかけですね。
この時、薩摩切子のことも思い出したんです。薩摩切子も木目金も、実は歴史のなかで一度、伝統が途絶えて人々の情熱によって蘇っている伝統工芸品。それが、何となく自分が“ゼロ”になった体験と重なって、とても共鳴して。
石巻の漁師も震災で船や帳簿、そして希望がなくなるような経験をして“ゼロ”から這い上がってきた人たちです。そういう人たちは、“自分にとって本当に大切なもの”を強く自覚し、活動の核にしています。
不思議なことに、私は“ゼロ”を経験した人やブランドと要所要所で必ず出会っているんです。その時は気づかないのですが、私の色彩活動において重要なヒントをくれる存在。出会いっておもしろいですね。
 <トップ画像アイテム>※()内すべて協力先
【島津薩摩切子】左から:オールドファッションドタンブラー[黄] /猪口(大)[紅] /麦酒器[金赤](鹿児島県特産品協会)
【本格焼酎】左から:伊佐小町(大口酒造)/さつま白波 七年貯蔵(薩摩酒造)/蔵の師魂(小正醸造)/一尚 ブロンズ(小牧醸造)
<トップ画像アイテム>※()内すべて協力先
【島津薩摩切子】左から:オールドファッションドタンブラー[黄] /猪口(大)[紅] /麦酒器[金赤](鹿児島県特産品協会)
【本格焼酎】左から:伊佐小町(大口酒造)/さつま白波 七年貯蔵(薩摩酒造)/蔵の師魂(小正醸造)/一尚 ブロンズ(小牧醸造)
十人十色の個性―生徒それぞれの「色」を活かす教育
―yukikoさんは教育機関にも携わっていますね。
「ファッションのスタイリングについて教えられる人を募集」という求人を見たのがきっかけです。企業での実務経験、カラーコーディネーターの知識もあることを買われて、ビジネスマナーや色を絡めた仕事も入ってきました。
―実際に、アパレルや美容業界を目指す生徒の皆さんと交流して、どのようなことを感じていますか?
周りと同調することで安心を覚える人が多いですね。または自己主張だけで、周りの意見を聞いたり仲間とのコミュニケーションを築くことが苦手な人もいると感じています。
学んで得た知識も大事ですが、「調和」や「コーディネート」は周りとのバランスを保ったうえでの表現です。だから色彩表現が豊富で上手な生徒はコミュニケーション能力に長けていることが多い。バランスのとれた“自己表現能力”を伸ばすことが必要だと思って教育に携わっています。
「十人十色」という言葉があるように「色=個性」であって、色を使いこなしているとは“個性”を発揮していること。私の授業では、どんな突拍子のない発想でもテーマやターゲットに合っているなら、まずは合格。ひとりひとりの個性をきちんと認めて、伸ばしてあげられるような環境づくりを意識しています。
 料理を彩るエディブルフラワー(食べられる花)。生産者の丹念な仕事と生命力ある花の色に魅せられ、ビジネスパートナーに。八芳園のレストランでは、手作りの海水塩をフレンドした脇坂園芸のフラワーソルトが採用されている。(協力:脇坂園芸・新潟県)
料理を彩るエディブルフラワー(食べられる花)。生産者の丹念な仕事と生命力ある花の色に魅せられ、ビジネスパートナーに。八芳園のレストランでは、手作りの海水塩をフレンドした脇坂園芸のフラワーソルトが採用されている。(協力:脇坂園芸・新潟県)
―ちなみに、yukikoさんご自身はどんな学生だったんですか?
今もそうですけれど、自分も他人も俯瞰的に観察しているような感覚で過ごしていました。スタイリストもモデルを客観視しながらスタイリングしますから、もとからスタイリスト気質なんですね。
グループではまとめ役になることが多くて、輪の中心で騒ぐより、騒いでいる仲間を外から見ているのが楽しいタイプ。盛り上がっていないと気になってテコ入れする……みたいな(笑)。クールに物事を捉えていましたね。
―学生の時、アルバイトは何かされていましたか?
総合商社の社員食堂で接客をしていました。田町のビルの最上階で、東京タワーが見える絶好のロケーション。そこでは商談とか会食がよく行われていて、世界各国の習慣や食文化を持つ人たちが集まりました。
文化の違いに触れたり、各国のビジネスマンのスマートな立ち居振る舞いを観察するのが好きでした。大人のカッコよさって容姿だけではないんだな、とか(笑)。
アルパの「音色」のなかにも、自分の色を見出して
 南米パラグアイ共和国の伝統的な手工芸品「ニャンドゥティ」の花瓶敷き。“蜘蛛の巣“を意味する繊細なレースで、民族衣装にも用いられる。(協力:アルパスタジオ ソンリーサ)
南米パラグアイ共和国の伝統的な手工芸品「ニャンドゥティ」の花瓶敷き。“蜘蛛の巣“を意味する繊細なレースで、民族衣装にも用いられる。(協力:アルパスタジオ ソンリーサ)
―yukikoさんといえばもうひとつ、アルパ演奏があります。そもそもなぜアルパを弾こうと?
たまたま地元の文化会館でアルパ演奏を聞いたのがきっかけです。始めたのが2010年の秋、仕事のピーク期でした。
アルパはクラシックハープより30cmほど小さくてパラグアイを中心に演奏されています。譜面がなく、自分の感性で弾くことができるので、右脳をフル活用するんです。講義の仕事が続くと左脳を酷使するため、仕事が忙しいほどアルパに入り込みます(笑)。
アルパがきっかけでペルーやチリ、アルゼンチンの人ともつながりができるようになりました。東京ビッグサイトや「スタイル プロモーション」のイベントでも演奏することもあり、皆さんがとても喜んでくださいますね。
―アルパの演奏が、yukikoさんの色彩活動にもつながっているんですね。
音楽って音色、「色」がついてますよね。私は物体の色だけではなく、感覚や精神も表現したいんです。音楽やその国の文化を「色=個性」として捉え、日本と比較をするのも楽しいですね。
―yukikoさんのように、好きなことから仕事につなげたいと思っている人に対して、アドバイスはありますか?
大事なのは知識を実践に変える力です。授業で学んだことや資格を、自分のライフスタイルのなかにどれだけ落としこめるかが重要だと思います。
やりたいことがあるのなら、まずはきちんと基礎を固めてから。 「型破りな演技は、型を知らずにはできない。型を知らずにやるのは、型なしというのだ」。 ……これは歌舞伎役者の坂東玉三郎さんの言葉ですが、まさにその通りだと思うんです。
仕事の場合は、世の中のニーズに合わせて表現方法を変えていかなければなりませんから、順応性や実践的なテクニックもきちんと学んでほしいですね。
自分の個性と向き合い、自身のスタイリングを楽しんで

―yukikoさんが目指すことや、今後やりたいことはありますか?
色彩・カラーといえば、「yukikoに任せよう」と思ってもらえるような人になることですね。焼酎に関する仕事も増えてきたので、スタイリストとして焼酎をもっと日本人のライフスタイルのなかに浸透させていきたい目標もあります。
特に「本格焼酎」といわれる焼酎は、芋焼酎なら“さつま芋、麹、水”の3つの天然素材から作られていて、無添加で飲む人に優しいお酒。原料がシンプルだからこそ、作り手がきちんと“本質”を捉えていないと美味しいものはできません。
ファッションも同様で、実はシンプルなコーディネートこそ、着る人の“本質”を一番表面化させます。ごまかしがきかない。だから“本質”を捉えて酒づくりをしている蔵元は人柄も実直で、皆さん魅力的なんですよ。そういう精神を持った人たちが手がけている本格焼酎を、多くの人に飲んでほしいですね。
最近は同世代である30代の蔵元や全国の生産者に目を向けています。個性豊かで才能と情熱があり、次世代を牽引する人たちの活動をスタイリストとして応援していきたい。私なりにエンドユーザーにうまく届けたいし、私自身も一緒に成長していけたら嬉しいですね。
―今後のyukikoさんの活躍が期待されますね! まとめとして、若い世代にメッセージをいただけますか。
ちゃんと“自分”という色を大事にすること。人と比べたりマネをするのではなく、きちんと自分に向き合って個性を発揮してほしいですね。
次のステップとしては、社会や相手のために“自分の色”をどれだけ順応させ活用できるのかを考えてみること。それが、コミュニケーションでもあり仕事に必要なスキルです。それができたら人のためにもなるし、何よりも楽しいはず。
色もファッションも、“選ぶ人の生き方”が現れます。是非、自分自身の「人生のスタイリング」を楽しんでくださいね!
<色彩総合プロデュース「スタイル プロモーション」> 〒107-0062 東京都港区南青山2-2-15-1317 地下鉄銀座線 青山一丁目駅より徒歩約3分[取材・執筆・構成・撮影]真田明日美 [取材場所]株式会社セレス


 30代鹿児島蔵元の挑戦!國酒・本格焼酎の“今”を生き、文化を築く!
30代鹿児島蔵元の挑戦!國酒・本格焼酎の“今”を生き、文化を築く!
 妥協をしないで、好きなものにこだわろう
―継続が、自分の道を作ってくれる―
妥協をしないで、好きなものにこだわろう
―継続が、自分の道を作ってくれる―
 「ハイブリッドファッションクリエイター」を名乗るJr.MARQUESとは何者か?
「ハイブリッドファッションクリエイター」を名乗るJr.MARQUESとは何者か?


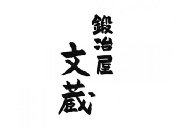

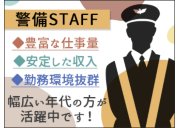







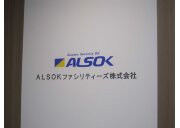





 バイト先の店長が怖い!苦手な気持ちとスマートに向き合う対処法まとめ
バイト先の店長が怖い!苦手な気持ちとスマートに向き合う対処法まとめ
 バイトを1日で辞めるときに電話連絡はOK?円満に退職するコツも紹介
バイトを1日で辞めるときに電話連絡はOK?円満に退職するコツも紹介
 バイトを3ヶ月で辞めることは可能?円満に退職するための知識まとめ
バイトを3ヶ月で辞めることは可能?円満に退職するための知識まとめ
 バイトに慣れるまでの期間はどれくらい?辛い状況を改善する4つのコツ
バイトに慣れるまでの期間はどれくらい?辛い状況を改善する4つのコツ
 契約期間内にバイトを辞めることは可能?円満に退職する4つのコツも紹介
契約期間内にバイトを辞めることは可能?円満に退職する4つのコツも紹介
 【例文】バイトを休むときの理由9選┃当日でも円満に伝えるポイントとは
【例文】バイトを休むときの理由9選┃当日でも円満に伝えるポイントとは
 ちょっと変わった特殊なバイト50選! 珍しいレアな仕事まとめ
ちょっと変わった特殊なバイト50選! 珍しいレアな仕事まとめ
 郵便局の年賀状仕分けバイト体験談35連発! 仕事内容や面接対策
郵便局の年賀状仕分けバイト体験談35連発! 仕事内容や面接対策
 【体験談あり】大学生におすすめの楽なバイト21選
【体験談あり】大学生におすすめの楽なバイト21選
 バイト面接の不採用サインBEST3! これを聞かれないとヤバい!?
バイト面接の不採用サインBEST3! これを聞かれないとヤバい!?